秋吉台国定公園では現在約2000種が確認されています。貴重種も多数生育しています。ここでは散策で見られる10数種類を取り上げてみます。
○オキナグサ(翁草) キンポウゲ科 3月~4月 山野の日当たりの良い草地に生える多年草。果期の羽毛の塊のような姿を老人の白髪にみたてた名。毎年、山焼き後の真っ黒な台地に毛むくじゃらの小さな芽を見つけると秋吉台に春が来る。、この頃に若竹山から秋吉台道路に沿い長者が森へ散策するコースの途中、咲いていることがわかるように小石で囲われています。花言葉は清純な感情、告げられぬ恋。
○ニオイタチツボスミレ(匂立坪菫) スミレ科 3月~5月 日当たりの良い草地など、明るく乾いた環境を好むスミレ。花弁は濃紫色から赤紫色で重なり合うように咲き、花弁の基部の三分の一ほどが白いので花の中の中心が白く抜けて見えます。花言葉は小さな愛、誠実。
○ハシナガヤマサギソウ(嘴長山鷺草) ラン科 5月~6月 日当たりの良い草地に生える多年草。距の長さが20mm以上。大型連休に入って草丈が低い草原で咲き始めます。高いものでも30cmたらずで、花の色も黄緑色と派手ではないのに良く目立ちます。
○ベニヤマタケ ヌメリガサ科 3月~5月 広葉樹林や杉林、ときに草地に散生するキノコ。地元では「アカバナ」と呼ばれ、親しまれてきました。
○カノコソウ(鹿の子草/別名ハルオミナエシ) オミナエシ科 4月~6月 山地のやや湿り気のある草地に生える多年草。ピンクの小さな花が集まった花穂が鹿の子絞りを思わせることからの名。花言葉は適応力、真実の愛情。
○コオニユリ(小鬼百合) ユリ科 7月~8月 山地の草原に生える多年草。茎は淡緑色、花は橙紅色。数個がまばらにつき、直径8cmほど。冠山ほか他所で見ることができ元気を与えてくれる花です。花言葉は情熱、賢者、陽気。
○カワミドリ(川緑) シソ科 8月~10月 山地の草地や林縁に生える多年草。名前の由来は不明。枝先に出た長さ5~15cmの果穂に、紫色の唇形花が密集してつきます。花は8~10mm、下唇は3裂し、雄しべ4個は花冠から突き出ます。茎や葉はスペアミントに似た香りがあります。花言葉は最後の救い。
○オミナエシ(女郎花) 7月~10月 日当たりの良い山の草原に生える多年草。全体の優しい姿からの名。葉は対生し、羽状に裂けます。茎の頂に多数の黄色の花が集まって上の平らな花群となります。花は直径3~4mmで上半部は5裂、雄しべは4個、雌しべは1個。花言葉は美人、はかない恋。
○サイヨウシャジン(細腰沙参) キキョウ科 7月~10月 中国地方と九州の草原に生える多年草。花の美しさを柳腰の美人に例え、根が沙参に似ていることによる名。ツリガネ人参の基本種で、花冠の先がわずかにくびれて、つぼ型となり花柱がもっと長く突き出します。花は淡紫色または白色。花言葉は感謝、誠実。
○ナンバンギセル(南蛮煙管)ハマソウ科 8月~10月 山野に生える1年生の寄生植物。花の形がキセルに似ていることによる名。すすき、みょうが、サトウキビの根によく寄生する。高さ15から20cmの高さの花柄の先に長さ3~4cmで淡紫色の筒状の花を横向きににつけます。とても不思議な花です。花言葉は物思い。
○ヒメヒゴタイ 山地の草原に生える2年草。株の葉は羽状に深裂し、上方の葉は裂けない。茎の上部で枝を分け、多数の赤紫色の頭花が傘型に密集し、頭花は球形で、直径1~1.6mm。希少種。![himehigotai[1]](http://ten-system.sakura.ne.jp/hisanaga/wp-content/uploads/2016/05/himehigotai1-300x197.jpg)
○マルバハギ(丸葉萩/別名ミヤマハギ)マメ科 7月~10月 山地に生える落葉低木。小葉は先が円く、小さな葉3枚からなるなり、茎から分かれた葉の根元より紫色の蝶形花が開きます。花は長さ1~1.5cm。がくは四つに分かれ、先は針状に尖っています。派手ではなく、しかし愛らしいこの花は武士の好む花だったようです。秋吉台ではマルバハギは 萩の仲間の中では一番多い種類です。
○カワラナデシコ(河原撫子/別名ナデシコ)日当たりの良い草原、河原などに生える多年草。葉は線形、花は淡紅色で直径約4cm。花弁は5個あり、細かく糸状に切れ込みます。暑いころはやさしいピンクですが、秋深まるにつれ、濃い色になります。花言葉は大胆、純愛です。
○センブリ(竜胆) リンドウ科 10月~11月 山野の日当たりの良い草地に生える一年草。古くから胃腸薬として知られ、千回振り出しても、まだ苦いということによる名。花は直径2~3cm。白色で紫色のすじがあります。リンドウと同じように、日が当たっている時だけ花が咲きます。リンドウ科に共通にいえる、凛とした花です。花言葉は義侠の愛、弱いものを助ける。![senburi031030[1]](http://ten-system.sakura.ne.jp/hisanaga/wp-content/uploads/2016/05/senburi0310301-229x300.jpg)
○リンドウ リンドウ科 10月~12月 山野に生える多年草。乾燥させた根茎を漢方では竜胆と呼び、その音からの名。茎頂や上部の茎と葉の付け根に青紫の鐘の花がつき、鼻の長さ4~5cmで5つに切れ込み内面に茶褐色の斑点があります。日が当たる時に咲き、陰ると閉じてしまいます。青紫がとてもきれいな花です。花言葉は悲しんでいるあなたを愛す。

 上はアキノキリンソウ(9月から10月) 右は アキヨシアザミ(10月から11月)
上はアキノキリンソウ(9月から10月) 右は アキヨシアザミ(10月から11月)
ウメバチソウ(10月~11月)
さらに詳しく知りたい方は「秋吉台で出会った花」中沢妙子発行の本 またはホームページ http://www.c-able.ne.jp/takosan/ を参照してください。











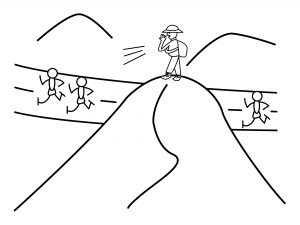





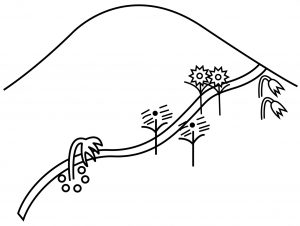
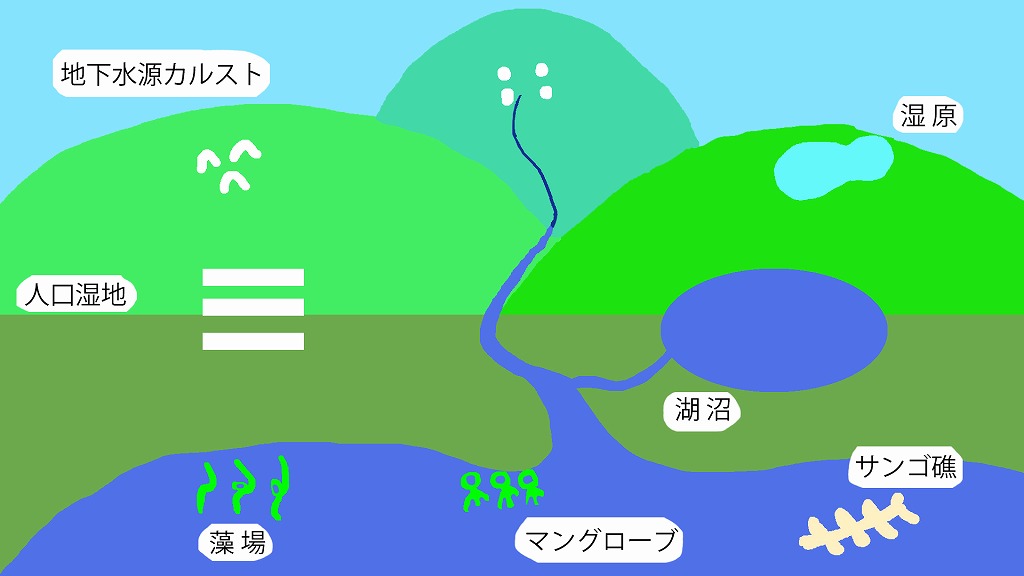
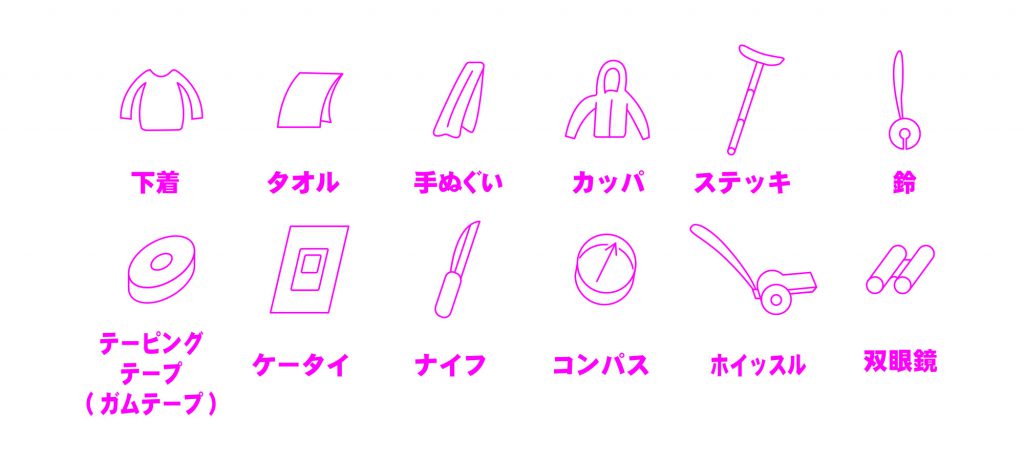



![himehigotai[1]](http://ten-system.sakura.ne.jp/hisanaga/wp-content/uploads/2016/05/himehigotai1-300x197.jpg)

![senburi031030[1]](http://ten-system.sakura.ne.jp/hisanaga/wp-content/uploads/2016/05/senburi0310301-229x300.jpg)


 上はアキノキリンソウ(9月から10月) 右は アキヨシアザミ(10月から11月)
上はアキノキリンソウ(9月から10月) 右は アキヨシアザミ(10月から11月)
 秋吉台東部に唯一、森が残っています。60余種の木々が生息する、原生林と言われています。中には古井戸の跡、女郎が池(泉)、祇があり、屋敷の跡が伺われます。
秋吉台東部に唯一、森が残っています。60余種の木々が生息する、原生林と言われています。中には古井戸の跡、女郎が池(泉)、祇があり、屋敷の跡が伺われます。




 星
星